本日、1・2限目の時間帯に、生徒が日常の学習・研究活動の成果を発表することで、主体的に学習する態度や創造性を高め、問題解決能力の育成及び高揚等を図るとともに、水産・海洋に関する理解促進や水産業及び海洋関連産業の一層の振興・充実に努めることを目的として、「令和2年度校内生徒研究発表会」を実施しました。発表時間は13分以内とし、各科代表者によって3題の発表および質疑応答が行われましたs。どの発表も非常にすばらしい発表でした。
なお、最優秀賞(海洋技術科)及び上位の優秀賞(水産食品科)の計2題は四国大会へ進出します(DVD審査)。



水産クラブ会長あいさつ 学校長あいさつ
<第1発表> 水産食品科3年(3名)
やってみ?おいしいけんSJKクッキング
~ケーブルテレビ、SNS等を使った水産物販売促進に関する研究~
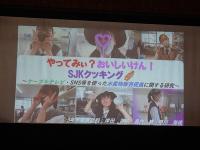

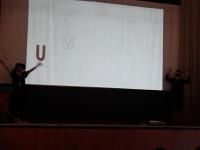
発表の様子


質疑応答の様子
<第2発表> 海洋技術科3年(3名)
全国初!高校生による焼玉エンジン復活プロジェクト
~やり切った3年間完結編~



発表の様子
<第3発表> 水産増殖科3年(3名)
MELDGs(メルディージーズ)
※MEL(水産エコラベル)とSDGs(持続可能な開発目標)を合体させ、MELDGsと名付け活動



発表の様子


質疑応答の様子



審査結果発表 最優秀賞(海洋技術科)表彰 優秀賞(水産食品科)表彰



優秀賞(水産増殖科)表彰 表彰を受けた代表生徒 審査員による講評
本日は6限目の時間帯に、学期に一度計画している「人権・同和教育ホームルーム活動」を実施しました。年間計画に基づき、各学年がそれぞれのテーマについて、真剣な態度で取り組んでいました。一人一人が差別のない学校、社会を作っていきましょう。
【1年生】
「様々な人権問題の解決への取組から学ぶ」では、目隠しをして視覚障害を疑似体験したり、活発に自分の意見を出す姿が見られたりしました。


【2年生】
「差別を解消する社会運動」・部落差別解消運動
愛媛の水平社運動を学んだり、班の意見をロイロノートを使って発表したりするなど様々な取り組みがなされていました。



【3年生】
「幸せな生き方」 ~結婚と差別問題~
3年生は、アンケート調査から幸せな生き方を一人一人が見つめなおしていました。
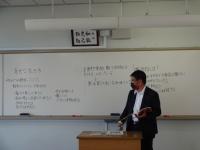
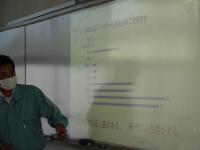

今日はマダイ親魚の選別・測定を行いました。まず親魚槽の水位を下げて1個体づつ掬い測定しました。


測定した67個体のマダイの平均全長44.6㎝、平均体長38.1㎝、平均魚体重2.6㎏でした。順調に成長しています!
測定後は水槽を洗浄しました。
一部の生徒は、海水を取水するためのストレーナーが汚れていたため洗浄しました。



ムラサキイガイ、ミドリイガイ等の貝類等多くの付着物がびっしりと詰まっていました。安定的に取水するためには定期的な掃除が必要です。
生物を飼育するためには飼育施設のメンテナンスもとても大事です。
私たち水産増殖科は地域の自然や生物、産業から学びを深めていきます!
本日、第29回水産食品科課題研究発表会が実施されました。今年度は、コロナ禍の影響で、例年のようにいろいろな人と協力しながらの活動が難しい状況でしたが、そのような中で、生徒のみなさんは工夫を凝らして研究に取り組んでいました。
また、はきはきとした口調で分かりやすく、丁寧な発表を心掛けていました。








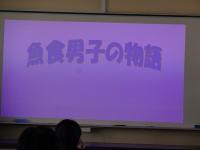

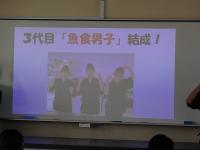



発表内容は以下の通りです。
【内容】(発表順、1班13分程度)
1 鯛の頭を使った製品開発
2 魚食男子の物語
3 虫取り隊長による害虫調査
4 宇和高校のHACCP導入への道
5 魚について知ってもらい隊
6 「コロナに負けん」宇和島の鯛もっと食べさいや!」
7 やってみ?おいしいけんSJKクッキング
☆彡新型コロナ感染症で大変な今、私たちが地元にできること
8 食品製造実習の工程動画の作成
9 河内屋蒲鉾のヒスタミン検査
今日は、水産増殖科課題研究発表会を行いました。3年生の皆さんは、3年間の集大成として発表をお願いします。1・2年生の皆さんは、先輩の発表を拝聴して今後の活動テーマの選定や学びを深めてください。
代表生徒あいさつの後、以下の発表順で行われました。
発表① 水生生物を題材とした教材開発
発表② 来村川干潮域におけるカニ類に寄生するフクロムシ



発表③ 未来の海を守ろう
発表④ 未来に残す豊かな宇和海 ~他人ごとを自分ごとに~



発表⑤ 宇和海の魚類でかるたをつくってみた その1
発表⑥ 宇和海の魚類でかるたをつくってみた その2



発表⑦ MELDGs・新魚種スマの育成 その1
発表⑧ MELDGs・新魚種スマの育成 その2
本発表会で最優秀となったチームは、11月4日に行われる校内生徒研究発表会で水産増殖科の代表として発表します。
審査の結果、『MELDGs』が選ばれました!。校内生徒研究発表会でも堂々とした発表ができるよう最終調整をしてください!



水産増殖科長の指導講評にもありましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により限られた時間での取り組みでしたが、各班しっかり発表することができました。
3年生の皆さんは、高校生活の仕上げが近づいています。悔いのない学生生活を送ってください。1・2年生の皆さんは、今回の発表を聞いて興味・関心を持ったことを早い段階から取り組めるよう準備をしてください。
最後になりましたが、今年度の課題研究を進めるにあたり多くの関係機関からのご指導・ご支援を賜りましたこと感謝申し上げます。
今日は秋晴れの中、坂下津の赤灯台で漁業実習(釣り実習)を行いました。前回の実習で作った仕掛けで、いざフィッシング!


釣果はイサキ、カサゴ、メジナ、カワハギ等です。予想したより少なかったですが、自分たちで作製した仕掛けで魚が釣れた感動を忘れないでください!


次回の実習では、今日、釣り上げた魚で観察とスケッチを行います。
私たち水産増殖科は地域の自然や生物、産業から学びを深めていきます!
本日は、2限目に1年生、3限目に3年生、4限目に2年生が「鑑定競技」に臨みました。生徒は自分の所属する科(海洋技術科(2・3年生はEコース・Fコースに分かれる)、水産増殖科、水産食品科)の問題(実技試験1問を含む25問、解答時間は1問につき20秒)に真剣に取り組んでいました。果たして結果はどうだったでしょうか?



会場入口で待機 いよいよ本番前 解答用紙



時間との闘い



あともう少しで終了


解答用紙提出
10月23日(金)
雨でグラウンドが使えない時には宮下ふれあい広場までランニングをし、95段の階段ダッシュをします。足はプルプルして・・・だそうです。



10月24日(土)
本校のグラウンドは狭いので時には宇和運動公園に行き、きめ細やかな指導のもと、思い切って投てき練習をします。




本日6,7限目の時間帯に「令和2年度人権・同和教育映画映写会」を実施しました。愛媛県で制作された人権に関する動画を鑑賞することで、いじめや人権侵害の防止と解消を身近なものと捉え、人権意識を高めることを目的に、進行は人権委員会の生徒が行いました。






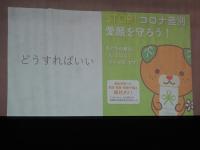


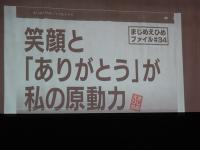
【映写会の内容】
(愛媛県庁ユーチューブ動画)
・愛顔を守ろう! 愛媛県人権啓発メッセージ
愛媛オレンジバイキングス 俊野 佳彦 選手
愛媛FC 有田 光希 選手 ほか
(愛媛大学)
・HELP US! ~エヒメで暮らす外国人のホントのキモチ~
(愛媛県警察)
・【中級編】ネット上での誹謗中傷(中・高校生向け)



終了後は、各ホームルームに移動し、感想文の記入を行いました。日頃から人権意識を高め、いじめや差別のない誰もが住みよい世の中を共に作っていきましょう。
本校では、愛媛県より「令和2年度SDGs推進リーダー校」の指定を受け、SDGsの観点を取り入れた学習活動を展開しています。今日は鶴島小学校に訪問し、交流事業を行いました。
開会式の後、学校紹介、南予の水産業について紹介しました。南予地域には魚類養殖、真珠養殖が盛んであることを理解できましたか?



次にアイスブレーキングでは私たちが作製した『宇和海のおさかなかるた』を使って、かるた大会をしました。かるた大会盛り上がりましたね!



その後、各ブースにより展示発表がありました。海洋ごみ、プラスティネーション標本、SDGsに関する内容です。



海洋ごみコーナーでは、和島市内沿岸で採取された大型ごみやマイクロプラスティックを顕微鏡で観察しました。プラスティネーション標本コーナーでは、サメ類やクルマエビ等の標本を手に取って観察していただきました。SDGsコーナーでは17の活動目標に関する内容について紹介しました。






鶴島小学校の皆さん、今日の学習はいかがでしたか?

次回は水産食品科による交流事業です。お楽しみに!
【2020年10月21日実施】